初回「愚者」、2回目「魔術師」、3回目「女司祭」、4回目「女帝」、5回目今までの4枚のまとめと「皇帝」、6回目「皇帝」、7回目「司祭」、8回目「恋人たち」、9回目「戦車」、10回目「力」、11回目「隠者」、12回目「運命の車輪」、13回目「正義」、14回目「吊るされた男」、15回目「死」、16回目「節制」、17回目「悪魔」、18回目「塔」、19回目「星」、20回目「月」
今回は「太陽」

このカードは、伝統的なタロットと絵が変わっていますね。昔のタロットの「太陽」には子どもが二人、でもウェイト=スミスのは一人で馬に乗っている。マルセイユにはないヒマワリも描かれている。

なんで変えたのか、ウェイトは語っていないけど、こういうことじゃないか?を生命の木のパスから説明していただきまして、おぉぉそういうことかー!と膝を打ちました。
「死」「月」「太陽」のつながりもお話いただけて、うれしかったです。

「死」は鎧を身に着けている、「太陽」の子どもは裸。
ウェイト=スミスとマルセイユ、「死」と「太陽」、カードを見比べると違いが見えてきます。「分類」がこの日のテーマということでした。
タロットなら、大アルカナと小アルカナに分けられる、小アルカナは数のカードとコート・カードに分けられる、数のカードはエースから10までの番号で分けられる、コート・カードはキング・クイーン・ナイト・ネイブに分けられる、分類して覚えますね。
人間も、年齢、性別、職業、芸風などなど分けられます。属性で分けるだけならいいけど、そこに良い/悪いの判断が入ってくると微妙。「名古屋人はドケチ」くらいなら笑い話でも、「ドレッドへアだと必ず職質される」だと偏見では?と私は思いますが、「警戒するのは当たり前」という人もいるだろうし。
こういう分け方の違いによっても、人は分けられてくんでしょうね。伊泉先生が例にされた学校時代の女子グループなんか、典型的だなと思いました。
でも、その分け方自体がどうなの?と問うてくるのが「太陽」のカード、ホドとイェソドをつなぐパス。

これがいいと自分で選んでるように思ってても、生きてきた環境や経験からなんとなく刷り込まれてきたものに選ばされてるのもあるんでしょうね。
たとえば、生まれたときから不景気だった今の人が、一生安泰の企業に就職したいというのはわかります。でもそれは本人の本当の望みなのかなとか、あまりにも就職だけを目標にしたら学生時代がかすんでしまうんじゃないかなとか、そんな早くから人生を決めちゃっていいのかなとか思います(大きなお世話)

ジョン・マイケル・グリア (著), 伊泉 龍一 (翻訳)
この本でグリアさんは懐中電灯に例えてますが、ひとつの目的に焦点を絞ると、ほかのものは闇に沈みます。
もともと空から降り注ぐ太陽の光はあっちにもこっちにも広がってるのに。わざわざ虫眼鏡で一点集中させて焼き焦がす、ようなこともやってしまってるのかもしれないな。

今回のお話を聴いて、あらためてカードを見ると、うん、カードのメッセージがぐいんときます。
早いもので、大アルカナ残り2枚となりました。次回は3/3(水)「審判」です。

カバラの生命の木から学ぶ「ウェイト版」タロット
講師:伊泉龍一先生
毎回夜8時~9時の1時間ずつ
受講料1回¥3,000
今後の予定:3/3「審判」、3/17「世界」
終わった回は録画配信できます。
- 5/13「愚者」
- 5/27「マジシャン」
- 6/10「女司祭」
- 6/24「女司祭」復習からの「女帝」
- 7/8 今までの4枚のまとめと「皇帝」
- 7/22「皇帝」
- 8/5「司祭」
- 8/19「恋人たち」
- 9/2「戦車」
- 9/16「力」
- 9/30「隠者」
- 10/14「運命の車輪」
- 10/28「正義」
- 11/11「吊るされた男」
- 11/25「死」
- 12/9「節制」
- 12/23「悪魔」
- 1/6「塔」
- 1/20「星」
- 2/3「月」
- 2/17「太陽」



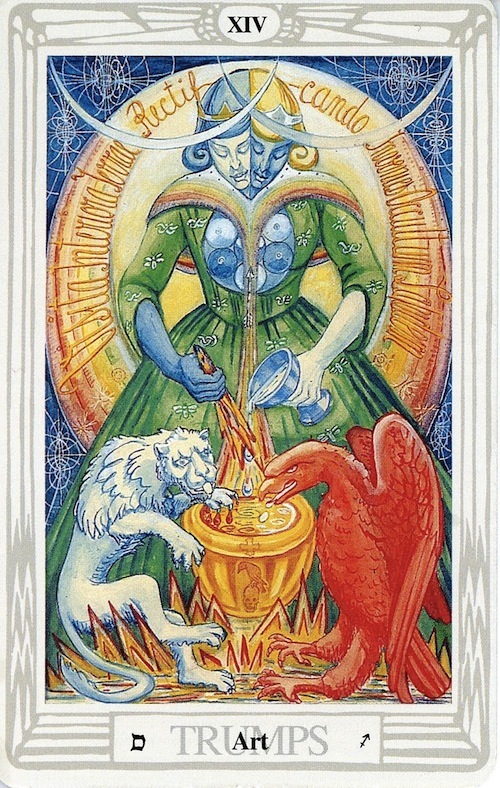
コメント